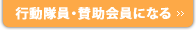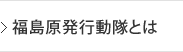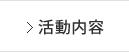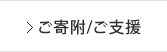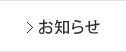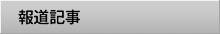6月7日(木)に参議院議員会館で開催した第17回院内集会では、平井吉夫理事が「福島原発行動隊と新しい老人文化」と題して講演を行いました。その内容は以下の通りです。(PDF版)
福島原発行動隊と新しい老人文化
公益社団法人 福島原発行動隊理事 平井吉夫
はじめに
今年の3月、福島原発行動隊がなかなか本来の目的である原発事故現場での作業に入れない状況を打開するため、主として対外アピールの方策を探り、実行することを課題とする戦略チームが設けられました。私はこのチームの一員として、福島原発行動隊の存在を文化運動としても位置づけることができないものかと考えました。そのためには行動隊の存在意義をあらためて確認する必要があります。その考察を進めていけば、われわれ自身も気づいていなかったわれわれ自身の存在意義が、浮かびあがることもありうるのではないか。そう考えて、思いつくことを思いつくままに書き留めていったら、153項目のメモになりました。
そこには私自身の考えもあれば、日ごろ接する行動隊の仲間の考えもあり、行動隊に異議のある人の考えも入っています。それを私は以下の九つのテーマに分けました。
・火災が起こったときに、まずなすべきことは? 消火か、火元の糾弾か?
・原点としての「決死隊」
・なぜ「シニア部隊」なのか
・なぜ行動隊はいまだに現場作業に就けないのか
・行動隊に参集する人びとの動機
・行動隊は待機する
・福島原発行動隊と日本の精神風土
・長期にわたる原発危機のなかで、シニア行動隊は文化になりうるか
・行動隊の歴史的意義。その発信力をいかに生かすか
そのメモを「福島原発行動隊の存在意義にかんする覚書」と題して戦略チームのメンバーと、金曜日ごとに開かれる自由参加の連絡会議にしばしば出席する人たちに配布し、それぞれ思いつくことを自由に書きこんでもらいました。いまそれをまとめているところですが、今回の院内総会にあたり、テーマを「行動隊の存在の特殊性」と「文化運動としての可能性」に絞り、ひとつの問題提起として、皆さんに聞いていただくことにしました。
行動隊の立脚点
福島原発行動隊は、福島第一原発事故の収束作業への参加を志願する、退役技術者・技能者・研究者を中心とするボランティア団体で、その事業目的は、原発事故の収束作業に当たる若い世代の放射能被曝を軽減するため、被曝の害が相対的に少ない高齢者が、長年培った経験と能力を活用し、現場におもむいて行動することである。
行動隊が結成されたころ、一部の反原発運動家から「事故の元凶である政府と東電に手を貸す行為」「政府・東電の責任をあいまいにする」という批判を受けた。いっぽうわれわれはこう考えた。町に火災が発生し、延焼し、もしくは延焼のおそれがあり、公的消防機関が機能不全のときは、火元はもとより町内こぞって消火に当たるのが先決であろう。火元には鎮火してから落とし前をつけてもらう。
〔ちなみに江戸時代には失火・出火は重罪であった。両国の川開きで鍵屋と花火の技を競った玉屋は天保14年に出火し、周辺半町に延焼させた咎で家産没収、江戸追放、家名断絶の罰を受けた。花火師はもともと銃砲の火薬専門家で、花火は火薬の平和利用だが、花火屋が江戸市中に店を構えるのは物騒なことであったろう。〕
火元にどんな過失があろうと、消火作業は実用本位に進めるほかはなく、その仕事に当たる者には白も黒もない。原発事故の「火消し」を目的とする行動隊は自発的参加者によって構成され、各人の思想、信条、あるいは心情はいっさい問わない。この原則は原発の是非についても同じであり、行動隊内には脱原発論者も維持論者もいる。この多様な構成員を結びつける唯一の絆が、原発事故の収束という大目的である。原発事故は他の災害とことなり、暴発すれば子々孫々におよぶ長大な時間と、地球規模の広大な空間にわたって深刻な被害をもたらす。それを阻止するためなら、われわれはだれとでもスクラムを組み、いま急務の火消しに専念する。
原点としての「決死隊」
現行動隊理事長の山田恭暉が原発事故の直後に「元技術屋」による「決死隊」の結成を呼びかけたとき、老人の在宅医療に尽力している老医師から、「老人は死んでもよいなんていう考えはとんでもないことだ」と批判された。「公的負担が9割の老人医療費のおかげで生き長らえた命を、粗末にするな」とも。
この批判は重い。行動隊の趣旨にたいする誤解は正すことができても、生命の尊厳を重んじる論旨に反論はできない。もちろんわれわれは、「それで万人が救われるなら老人は死んでもよい」と、一般論としては絶対に言わないし、思ってもいない。しかし、「それで万人が救われるなら“自分は”死んでもよい」と、個別論としては思っている。あくまでも自由な個人の主体的な選択として。
福島原発行動隊は2011年3月30日付の山田が旧知の人びとに送った「福島原発冷却系復旧老年決死隊の結成提案」に始まる。そこでは「決死」という言葉が4回も使われている。4月6日付の公式(一般向け)の「呼びかけ」には「決死」は一語もないが、これに呼応した人びとの大部分は決死隊と認識したはずである。行動隊発足当初の内外メディアの反応も、やはり「決死隊」という見方が多かった。海外メディアには「自殺部隊 suicide corps」という言葉が散見し、中国のテレビは「敢死隊」と呼んでいた。
「決死隊」という言葉は東電内でも使われたらしい。事故発生直後の危機的状況に直面したとき、現場では40歳代と50歳代の「決死隊」が防護服と耐火服に身を固めてベント操作に当たったという。しかし髙線量のため、第一次隊は短時間しか作業ができず、第二次隊は作業現場にも到達できなかった。これは決死隊と言えるであろうか。
では「老人決死隊」なら髙線量下でも作業を続けるのか。
答え1。そのとおり。そうでなければ労働適齢期を過ぎた老人がわざわざ出動する意味はない。
答え2。いや、主体的な意志にもとづく自発的行為といえども、それは法的にも倫理的にも許されない。
答え2が、健全な常識、一般的な社会常識であろう。しかし非常時において超法規的な非常手段がとられることは、さまざまな事例で見られる。2011年の4月末の新聞報道によれば、小沢一郎元民主党代表は原発事故による災厄を終結させるため、超法規的措置として決死隊を投入する「政治的決断」の必要性を語ったという。
また、菅直人首相は事故直後に現場からの撤退を申し出た東電幹部にたいし、「60歳以上が現場に行けばよい。私はその覚悟でやる」と叱責し、海江田経産相ほか側近議員にも、「この事故に命をかけている。放射能障害問題を考えたら、ある程度世代の高い人がやったほうが相対的には影響が少ないとされている」と述べたそうである。
非常事態における苦渋の、だが当然の発想。これは行動隊結成の原点でもある。
自己犠牲? 捨身? グスコーブドリ(宮沢賢治)? それとも特攻隊? 人柱?
そういう悲壮な意識は、行動隊にはまったくない。われわれが目的とする行動は、個々人の自由かつ合理的な選択である。
行動隊の中核は、放射線計測の専門家、各地の原発の設計・建設・維持・管理に携わった者、建設関係の各種資格所持者、電気工事関係の各種資格保持者、自衛隊出身者など、多彩な知識と豊富な経験を有する技術者・技能者・研究者で構成されている。われわれが重んじるのは冷静かつ理性的な思考・思惟・行動であり、ファナティシズムやヒロイズムとはまったく無縁である。もちろん作業に当たっては最大限の安全措置を講じるであろう。現在の事故収束作業現場(および各地の原子力施設の通常業務)にかんしても、行動隊は被曝管理、健康管理体制の抜本的な整備を政府と東電に提言している。
それでも、必要とあれば、行動隊は命を賭して現場におもむくであろう。
なぜ「シニア部隊」なのか
高齢者は放射能被曝の害が相対的に少ない。疫学的・統計的に確たる証拠を示すデータは未見であるが、おそらくそうだと一般に思われている。少なくとも心理的には、老人は放射能にたいして若者よりも強い。
たとえ被曝が原因で発癌しても、どっちみちそのころには寿命が(ほぼ)尽きているし、もう子供はできない(つくらない)ので遺伝的影響もない。
老い先が短い。もうたっぷり生きてきた。天寿を(ほぼ)全うしている。いつ死んでもよい。それでお役に立つなら本望。そもそも死への恐怖心が薄れている。死の恐怖は生存本能に起因する。生存本能は「種の保存」本能に由来する。老人はその任務を果たし終えた。生存本能が稀薄になっている。(鮭は産卵すると死ぬ。)
退役技術者・技能者が培った積年の知識・経験・能力を活用・再利用する。亀の甲より年の功。
〔ちなみに、クリント・イーストウッドが監督・主演した『スペース・カウボーイ』という映画(2000年)がある。40年前に打ち上げた通信衛星が故障し、その旧型衛星を修理できる人間は40年前にプロジェクトにかかわった技術者しかおらず、退役した4人の老人が宇宙に飛び立つという筋立て。これはわれわれのシチュエーションを彷彿させる。〕
そしてなによりも、老世代は原発問題にかんし、自らの社会的責任を問われている。
そういう老人が若い世代の放射能被曝を軽減するため現場におもむいて作業に当たる。若者には深刻な結果をまねきかねない被曝を、被曝の害の少ない老人が肩代わりする。これはきわめて合理的な発想ではないか。
とはいえ合理性は諸刃の剣であり、合理的であればなにをしてもよいわけではない。ファシズムは究極の合理性の追求であった。ナチスが行なった「合理化」には心身障害者の抹殺政策(T4作戦)もある。そこで想い起こすのは先述の老人医療専門医師からの批判である。ひょっとしたらこの老医師は、老人決死隊の発想に「棄老」のにおいを嗅いだのではないか。
棄老の古典的な例は姨捨伝説である。姥捨の慣習が実際にあったかどうかは知らないが、もしあったとすれば、これも極貧の村落が生き残るための「合理的」な方策であったろう。もちろん棄てられる老人は犠牲者だが、『楢山節考』(深沢七郎)のおりん婆さんは自発的に、喜んで、姥捨山に入った。そういう老人もいたかもしれない。では姥捨とシニア行動隊とのちがいはなにか。
そういう設問自体がナンセンスで、両者は類比にならないことを承知のうえで、すこし考えてみる。おりん婆さんの楢山入りの背景には、貧しい村落共同体の強制的な因習がある。そして自発的に山に入る老人は称讃され、拒む老人は非難されたであろう。これは「空気」であり、おりん婆さんはそれに従った。いっぽう行動隊のシニアは孫の世話で天寿を全うしてもだれにも咎められることはないのに、自発的に被曝のリスクをとるのである。そういうリスクとりを、たとえば政府が国民運動として唱導するならファシズムそのものであるが、さしあたり日本では、テレビや週刊誌で「奇特な人たち」と冷やかしまじりの賛辞はうけても、強圧的な「空気」になったりせず、リスクとりは個々人の理性と自由意志にもとずく選択にとどまっている。
犠牲的奉仕と日本の精神風土
行動隊の結成にいちはやく反応したのは海外のメディアであった。かれらがとくに注目したのは「自己犠牲」「カミカゼ」である。西洋にそういう思想はないと、二、三の海外ジャーナリストは言った。(そんなことはない。私のわずかな知見によっても、歴史上そういう事例は西洋にも東洋にもいっぱいある。)
哲学者の加藤尚武氏は「現代の日本に定着している倫理性」を三つの原型に分ける(『災害論―安全性工学への疑問』世界思想社、2011年)。
(1)打算的相互性の倫理
(2)非打算的相互性の倫理
(3)非打算的献身・貢献の倫理
相互性とは、なんらかの見返りを期待すること。(1)は、見返りがなければ人助けをしない。(2)は、動機に打算はないが、やはり見返りを期待する。(3)は、いかなる見返りも期待しない、一方的な貢献。わが国の日常的な倫理にはこの三つが混在している。
そして加藤氏は福島原発行動隊の例を引き、このような自己犠牲的奉仕を英語では「スーパーエロゲーション」「義務を超えた行為」「功徳」といい、その成立条件は、①有効であること(功利性の観点から否認されない。主観的献身は不可)、②自発的であること(兵士の場合、兵役拒否権が認められなければ功徳は成り立たない)、③自分の得る利益を顧みないこと(保険金目当ての自殺は功徳にならない)、と述べている。
行動隊の倫理は(3)の非打算的献身・貢献の倫理であり、スーパーエロゲーションの三つの条件とともに、たいていの一般ボランティアにも当てはまるものである。ただし行動隊の場合は「決死隊」の要素があり、ここが一般ボランティアと大いに異なる特殊性である。この決死隊の「自己犠牲的奉仕」を、二、三の西洋のジャーナリストが日本特有のものと見たのは、おそらく「カミカゼ」からの連想であろう。
たいていの場合、決死隊的行為が必要となるのは戦争である。しかし戦闘員が確実に死ぬことを前提にした戦術(神風特攻隊)を正式に軍制に採り入れた近代国家は、たぶん日本だけであろう。人間魚雷はイタリアでも第二次大戦中に採用したらしいが、あれは人間が魚雷の外部(魚雷にまたがる)で操縦して敵の艦底に近づき、発射とともに人間は待避するのがタテマエであり、日本の回天のように人間が魚雷の内部で操縦し、そのまま「肉弾」になる戦術ではない。戦闘員の確実な死を前提とする戦術は兵の邪道である。
日本にはこの特攻隊を讃美する精神風土がある。いっぽうイスラム過激派の戦術である自爆攻撃は、たいていの日本人が嫌悪する。
〔9.11のさいに海外メディアはあれをしばしば「カミカゼ」と呼んだが、多くの日本人が「あれとカミカゼとはちがう」といって怒った。これには異文化への偏見や拒否感もある。〕
自爆攻撃を嫌悪するのは健全な精神であり、健全な精神は「肉弾」を前提とした特攻隊も嫌悪しなければならないはずである。行動隊は絶対に特攻隊ではない。「死を前提とした奉仕」と「死をも覚悟した奉仕」とはまったくちがう。
2001年1月、JR新大久保駅のプラットホームから転落した乗客を助けようとして死んだ、日本人と韓国人の青年の事例はどうであろうか。二人の青年は電車が入構する前に助けることができると思って線路に下りたにちがいない。しかし間に合わず、転落した乗客もろとも電車に轢かれ、尊い命を犠牲にした。線路に下りるとき、二人は死を覚悟したわけではないだろう。しかし「死ぬかもしれない」と思わなかったかどうか。いずれにしても非常に危険な行為という認識はあったはずである。
この事件は世間に深い感銘をあたえた。駅には記念碑が設けられ、映画化され、プラットホーム転落防止措置が格段に進んだ。二人の青年の行為を「無謀」「命を粗末にする」と批判する意見はまったく聞かれなかった(あるいは、おもてに出なかった)。このように、自己犠牲的奉仕には〔それが良いのか悪いのかは別にして〕強烈なインパクトがある。
行動隊が参院議員会館で定期的に開いている集会で、放射能防護服を着用しての作業の困難さが話題になったとき、一人の出席者が「自分は防護服なんか要らない」と発言して、場内の笑いを誘った。この笑いは、「その意気は壮とするけれども、やはりそういうわけにはいかないよ」という、共感まじりの否定、内に秘めた覚悟と世間の常識とが健全に結合した反応であろう。
われわれが現場作業に当たるのは、被曝の危険度が通常よりも高く、将来のある若い世代に任せるには躊躇する場合であるが、もちろんわれわれは可能なかぎり最高度の安全措置を講じたうえで仕事をする。これは「常識」である。とはいえ高濃度被曝の「覚悟」は胸底に秘めている。行動隊の趣旨に賛同こそすれ、異を唱える声がほとんど聞かれないのは、この点に共感するからであろう。
しかしわれわれは自己犠牲的奉仕を強制はもとより勧告・勧誘もしない。趣旨を示し、賛同と支援を呼びかけるだけで、参加するかしないかは徹頭徹尾、本人の主体的な意志に任せる。そして否定的意見にたいし(誤解があれば真意を説明するが)反論はしない、というか反論できない。
そもそも自己犠牲の称揚は(ほぼ)必ず強制に、圧力に、拒否できない「空気」の醸成に転化する。これもわが国の精神風土である。苦い経験は、戦時の極限状況から平時の日常生活に至るまで枚挙にいとまがない。これは定款に「原発事故収束に自発的に参加する国民意識の涵養を図る事業」を掲げる福島原発行動隊が、いちばん気をつけなければならないこと、おそれなければならないことのひとつである。
さらに、これはどこの国にもあることかもしれないが、日本的精神風土の悪しき側面として、「空気」に流される、自主判断力が弱い、情報処理能力が弱い(一方的な情報を信じこむ)、風評の猛威、個の自律性が稀薄、ムラ社会、等々がある。これは利己にも利他〔それも往々にしてファッショ的〕にも働き、先駆的・創造的な試みを阻害する要因になりやすい。行動隊の呼びかけが、これにどういう影響をあたえるのか、これとどういう関係にあるのか、さまざまな側面から考察することも、われわれの課題であろう。
文化としてのシニア行動隊
かつては「奇特な人びとの慈善」であったボランティアの精神と活動は、「ボランティア元年」と呼ばれる1995年の阪神淡路大震災での被災地支援を機に、わが国でも急速に普及した。それはひとつの文化になりつつある。あるいは、すでに文化になっている。
制度もしくは慣習としての「困ったときの人助け」は古今東西を問わず、どこの共同体にもあり、地域社会の文化にもなっている、あるいはなっていたが、これは加藤尚武氏のいう「打算的相互性の倫理」にもとづく相互扶助である。われわれの子供のころ「勤労奉仕」というのがあり、これは一方的な無償の行為で、いまのボランティアに近いけれども、戦中はもちろん戦後も強制動員の嫌いがあった。
ボランティアの条件・基本要素は、自発性、無償性、利他性であり、近ごろそれに先駆性が加わった。四つ目の先駆性とは、既存の社会・行政システムにない機能を創造的かつ自発的な発想で補完する役割を担うこと。原発事故収束作業へのボランティアは、なにしろ前例がないことなので、まさしく先駆的である。ふつうボランティアというとアマチュア集団をイメージしがちだが、医師や教師など専門家を結集した活動もあり、とくに「プロフェッショナル・ボランティア(プロボラ)」と呼ばれることもある。退役技術者・技能者を中核とする福島原発行動隊は「プロボラ」である。
ボランティアを「国民文化」にしようとする動きには、二つの側面がある。ひとつは、ボランティアを実践している人びとの自然な願望。これは愛や慈悲を説く宗教者の布教に似ている。いまひとつは、主として教育課程に組み入れて義務化する動き。また進学や就職などでボランティア活動の経験が評価点になったりして、ボランティアが利益目的、対価を得る手段になることもある。まさしく打算的相互性の倫理。これをボランティアと言えるであろうか。かつて安倍晋三首相が提唱した「大学入学前のボランティアの義務化」などは、明らかに徴兵・兵役の代替が念頭にあった。
福島原発行動隊は、原発事故という特殊な災厄を契機に、老人にしかできないボランティアの可能性を示した。厚労省の調査によれば最大のボランティア人材源は主婦と高齢者である。高齢者が多い理由は「老人は暇がある」からで、そのボランティアの主眼は労働力不足の補填、もしくは人件費の節約であり、本来なら労働適齢期世代が有償でなすべき仕事であろう。いっぽう行動隊のボランティアは「老人であるからこそやれる」仕事であり、若者は「やってはいけない」のである。そこに老人文化の新たな可能性を見いだせないであろうか。
残念ながら私の頭では、いまのところ「可能性」としか言えない。具体的なイメージはわれわれの活動が進展する過程で見えてくるであろう。この「老人文化」は、下の世代(上の世代はない)の倫理上の文化、あるいは一般的な徳の文化にたいし、なにかを発信できないだろうか。なんらかの影響、あるいは補完の作用を。「年寄りがあんなにがんばっている、若いわれわれもがんばろう」から始まってもいい。それは旧来の「敬老精神」にはないものである。
いま社会福祉法による「老人の日、老人週間」、祝日法による「敬老の日」があるが、いずれもその趣旨は、長寿を祝い、多年の労をねぎらい、社会に尽くしてきた老人を敬愛する、というもので、老人の知恵を借りる姿勢はあっても、「もうひとはたらき」をうながすモチーフは稀薄である。高齢者を「保護すべき対象」とは見ても、「頼りにする対象」とは見ていない。
この旧来の敬老精神は、われわれ行動隊を「敬遠」する理由にもしばしば使われる。お年寄りを過酷な環境で働かせるのはしのびない、というわけ。昨年7月26日の参議院内閣委員会で牧山ひろえ議員が「志願している退役技術者を作業員に加えるべきではないか」と質問したときの細野原発事故担当相の答弁、今年3月22日の参議院環境委員会で亀井亜紀子議員が「なぜシニア行動隊を活用しないのか」と質問したときの細野環境相の答弁も、この趣旨によって行動隊を現場作業に活用しないことの言い訳にしている。
この二つの細野大臣の「敬老」答弁は、「必要になれば退役技術者の助力をお願いすることもありうるが、いまのところ作業員は質量ともに充分に足りている」という理由付けとペアになっていた。
福島原発行動隊は、このような旧来の老人観を打破するものである。われわれの存在と活動には、老人独自の社会貢献から生まれる新たな老人文化の種が宿っており、それはシルバー人材センターや生涯学習、寿大学や隠居の盆栽趣味などとは次元を異にしている。ちなみに「旧来の老人観の打破」とは、「アンチエイジング」や「脱老人」を意味するものではない。われわれが生理的にも制度的にも老人であることは厳然たる事実であり、それを認めたうえでの、というかそれを逆手にとっての自己主張である。
行動隊の歴史的意義と発信力
老人にしかやれないこと、若者がやってはいけないこと、それが行動隊の仕事である。そんな事例がいまだかつてあったであろうか。
老人にしかやれない仕事というのは、場合によってはいくらでもある。つい先日も、江東区が江戸前和船の復興を企画したが、和船を造る技術を継承した現役の職人がおらず、引退した老匠に頼るしかなかったという報道を目にした。しかし若者がやってはいけない仕事という条件が重なると、寡聞にして私はその実例を知らない。
〔物語の世界ならそういうシチュエーションも考えられる。たとえば有毒ガスの噴き出す火口に埋蔵するダイヤモンドを採取するのは老人の役目で、働き盛りの世代には禁じられている村、とか。〕
福島原発行動隊の事業目的は、本来なら労働適齢期世代のなすべき仕事が、特殊な事情のため、労働適齢期世代とその子孫に深刻な害を及ぼすおそれがあるので、被害の比較的少ない労働適齢期を過ぎた先進世代が、後進世代の肩代わりをすることである。
これは、おそらく世界でも史上初めての試みではなかろうか。原発事故という、20世紀後半からの人類の営みがもたらした前代未聞の災厄、それがシニア行動隊という前代未聞のプロジェクトを喚び起こしたのである。
〔その意味では、行動隊は現代社会の負の遺産の清算者とも言える。〕
行動隊は実際に発生した原発事故に対処するために発足した。ありうべき事故にそなえて事前に結成されたのではない。もし3.11の前に行動隊が存在し、社会的認知を得ていたら、先引の菅首相の「60歳以上の人間」云々という言辞からしても、事故直後の東電が言うところの「決死隊」行動に、なんらかのかたちで、かかわっていたかもしれない。
そして行動隊の社会的認知が確立すれば、世界じゅうの原発保有国において、ありうべき事故にそなえた類似のシニア部隊が結成される可能性もある。それが、われわれのようなボランティア団体であるにせよ、国家が組織する公設団体であるにせよ。
〔国家組織の場合はおそらく退役軍人(主として工兵)を中核とする編成になるであろう。もし退役軍人が若い現役兵士の被曝の肩代わりを申し出たら、社会的影響、世論の喚起力はきわめて大きい。それは言い出しっぺのわれわれとまったく同じ発想であり、いかなるかたちにせよ、連携する価値は充分にある。ちなみに退役自衛官の団体である「隊友会」が福島原発行動隊に関心を示し、山田理事長が今年の4月に面談した。残念ながら隊友会にそういう篤志はなさそうである。〕
ありうべき事故にそなえた原発行動隊は各国別であるとはかぎらない。医療関係者のプロボラが国の枠を超えて国境なき医師団を結成したように、国境なきシニア原発行動隊が結成される可能性も、場合によってはあるかもしれない。こういう壮大な展望も、わが福島原発行動隊には開かれていると思いたい。
ことほどさように、福島原発行動隊の先駆性、創意性、そして歴史的意義は大きい。この歴史的意義が有する潜在的な発信力を、いかにして顕在化するか。これは行動隊が確固たる社会的認知を得るための重要な課題である。そのための最も有効な方策は、もちろん原発事故収束にかかわる作業を実践することで、行動隊の最強の決め手は行動することであるが、行動隊の存在を文化運動として位置づけることも、戦略のひとつになりうるのではないか。
その手だてとして、すぐ思いつくのはプロパガンダとデモンストレーションである。シンポジウム、講演会、辻説法、出版活動、各種メディアの利用、意見広告、ネット展開、等々。そのためにはシニア行動隊の「哲学」を考究し、深め、それを明解に表現しなければならない。識者の協力を仰ぐことも必要である。思想界・文化界の権威者に働きかけ、知恵を拝借し、発言してもらう。そういうことを業とする(元・現)出版編集者やジャーナリストを動員し、ひと役買ってもらうのも、ひとつの方策であろう。行動隊の中核は理系の人たちであるが、ここは文系の行動隊員・賛助会員の働きどころである。
原発にまつわる危機が終焉したときに、福島原発行動隊が文化遺産としても記録されることを願って、皆さんの知恵と力を寄せていただきたい。