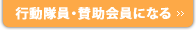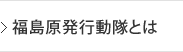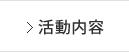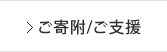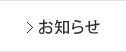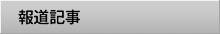私は過去77年の人生で、三度、命拾いをした。
最初は、敗戦後、旧満州の新京(長春)。ソ連軍の侵攻、国民党の支配、八路軍と国民党の内戦−−1947年夏の引き揚げまでの2年間、毎日を命からがら、生き延びた。ソ連軍占領下、憲兵の宿舎となった我が家では、拳銃の暴発、手榴弾をつかんだ将校同士の喧嘩など、ヒヤヒヤの連続。外では、毎朝、日本人の行き倒れが見られ、中には自動小銃バラライカで撃たれた人もいた。
日本降伏時、ハルビンにいた父は、ソ連軍に逮捕され、シベリア抑留から戦犯裁判、20年の重労働刑に服役。スターリン死去の恩赦で、1953年、ようやく釈放され帰国した。だが、祖母は息子の「逮捕・投獄」の報を受けた直後、倒れ、そのまま他界した。叔父の一人は、現地招集され、国境近くで戦病死。その妻の叔母も、間もなく激度の腸結核で、なす術も無く、私たちの目前で逝き、近所の公園で荼毘に付した。
続く、国共内戦は激しい市街戦——迫撃砲が頭の上を飛び交い、重機関銃の掃射が姉の頭上10cmの壁を破った。だが、幸いに、私たちは1947年夏に長春を離れ、同年冬の悲劇(「卡子(チャーズ)」=膠着した国共軍前線に挟まれた日本人居留民の大量餓死・凍死の事件)を免れた。
こうして、祖父と母、3人姉妹と私の6人は、無事、帰国。長兄(予備学生で台北帝大から海軍飛行隊に入り、厚木の特攻隊基地で後方勤務)と次兄(大連の南満工専で終戦を迎え、貴金属ブローカー。商売敵の中国人を殴り、殺人未遂で逮捕されたが、公安署長の温情で釈放され、別途帰国)に、東京で合流した。兄弟姉妹6人、奇跡的に、戦争で一人も欠けなかった。
2回目は60年安保、6・15。死ぬ気だった。「おミッチャン、今日は何人殺す気だい?」と哲学の同僚、廣松渉が私に尋ねた。国会議事堂南通用門の向かい側、歩道のやや高くなった土手の上、清水幾太郎さんと娘の禮子さんもいた。私は東大駒場のデモ隊の末尾にいて、国会の周りを数回回り、南通用門に来て、一息入れたところだった。廣松の質問は、「相手を何人殺す気か」、ではなく、「学生の側の犠牲者が何人と予想されているか」、と云うものだった。私は「さあ、7、8人かな」と答えた。その中に、自分は入っていた。何人かの死以外に、岸政権を倒すことは出来ない、新安保条約の発効阻止は出来ないと考えていた。だが、樺さんの死は「想定外」だった。機動隊に国会構内から押し出され、催涙ガスに咽びながら、三宅坂を下る途中、島成郎が「死んだのは樺さんだ」と伝えた。身が震えた。二人とも、しばらく無言だった。生きていることが口惜しかった。
3回目は、1982年。オーストラリア南部の葡萄畑の中を走る幹線道路。キャンベラからアデレイドへ、引っ越し荷物を満載して走る2トントラックの座席に、妻と娘と私の3人が座っていた。ハンドルを握っていたのは妻だった。時速は100キロを越えていた。突然、バンという音と共に、車が揺らぎ始めた。パンクである。やがて、車はゆっくりと、何回も横転しながら、葡萄畑に突っ込む直前、道路脇で止まった。(妻のブレーキの掛け方は、雪のニューヨーク州北部で鍛えただけあって、反射的なパンピング。見事だった。)回転する間、フロント・ガラスが一瞬で壊れ、まるでスロモーション・カメラの映像のように、座席周辺の物—−魔法瓶、弁当箱、バナナ、ポシェットなどが、次つぎと壊れたフロント・ガラスの枠の外へ、投げ出されて行った。幸い、3人は、みなシートベルトをしていたので、身体は車体を離れなかった。していなかったら、確実に、道路上か葡萄畑に頭から着地していたことだろう。事故の原因は、レンタカーの会社が後部車輪を2重にしていなかったためと判明。調停で勝利して、荷物の賠償金を戴いた。
このように、3度命拾いをして長生きし、さあ、余生を楽しもう−−「面白くてためになる(自分にも、ひと様にも)残り人生を送ろう」と思っていた矢先、3・11。大きな揺れを、伊豆の自宅で感じながら、「ああ、何かしなければならない時が来たな」と思った。凄まじい津波の映像、深刻化する福島第一原発事故。そして、山田アピールに接した。すぐさま、賛同。
その中、思わぬ衝撃が別のところから来た。膝の痛みを訴えていたサッカー少年の孫(11歳の男子)が、骨肉腫と判明。原因不明、100万人に一人か二人の難病である。3・11、原発事故とは、勿論、因果関係はない。しかし、福島原発事故の収束を、やれるもの全員が全力で図らなければ、孫のようなガン患者が確実に増える。確率論的に増える。
私は文系で技術・技能無し。高血圧、脊柱管狭窄症で足腰の痛み絶えず、体力無し。また、この先、研究成果の出版を控えているので、すぐさま、福島に作業要員では行けない。山田理事長他の皆さんのように、全力投球は出来ない。しかし、福島原発行動隊のプロジェクトには心から賛同し、出来る限りの応援、協力をします。三度生き延びた老人の呟きです。